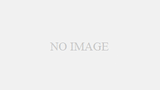かつて自己責任論を振りかざしていたが、今は改心した人。
こういう人には、とにかく優しくすることが大切です。
なぜなら、彼らの改心は、社会全体にとって大きな意味を持つからです。
改心者は「説得力のある味方」になる
自己責任論を信奉していた人が、さまざまな体験、挫折を経て、その考えを変えたとき、その言葉には大きな説得力があります。なぜなら、彼らはかつて自己責任論を支持していたからこそ、同じ価値観を持つ人々に響く発信ができるからです。
実体験に基づく共感力は、そうかんたんに座学(お勉強)で獲得できるものではありません。
たとえば過去に「福祉は甘え」「努力すればなんでも乗り越えられる」と主張していた人が、以下のような問題から、心身が満足に活用できなくなり、その結果として社会的な自身の立場が変わったとします。
- 病気
- 事故
- 事件の被害者になる
こうした、ときに避け得ない変化によって、社会におけるこの人の立場が変わり、「社会の支援なしでは生きていけないことがわかった」と発言するようになったとします。その発言は、現役の自己責任論者にとって、耳を傾けざるを得ないものになるでしょう。
この点は、ベトナム戦争後のアメリカを見ても明らかです。戦争支持派だった兵士たちが、負傷して帰還した後に反戦活動の主力となりました。彼らは単なる理想論ではなく、実体験に基づいて「戦争の現実」を語ることができたため、多くの人々に影響を与えたのです。
同じように、自己責任論を唱えていた人が「あの考えは間違いだった」と発信することは、社会全体の意識を変える大きな力になりえます。
改心した人を攻撃するのは逆効果
- 「お前は昔、自己責任を叫んでいたくせに!」
- 「自業自得だ!」
と非難したくなる気持ちもあるでしょう。それは理解できます。しかし、それではせっかくの貴重な「社会の変革者」を失うことになります。
改心した人を叩く社会においては、改心した人は非難されることを恐れ、口をつぐんでしまいます。今は匿名性の高いSNSがありますので、別人格を演じて「福祉は重要だ」などと主張することはあるかもしれません。ですが、自己責任論を振りかざしていたときの人格とは切り離された形で表現活動を行うことは、すでに述べた事実に照らして言えば、非常にもったいないことだと言えます。
むしろ、彼らが改心した後は温かく受け入れ、「その経験を発信してほしい」「あなたの体験を聞かせてほしい」と促す方が建設的です。「自分はかつて間違っていたが、今は考えを改めた」という証言が増えれば増えるほど、社会に伝染病のごとく蔓延する自己責任論は力を失い、崩れていくからです。
さらに、人間は怒りをエネルギーにして行動することがよくあります。かつての自己責任論者が「自分はこんなに苦しんだ」「あの時の自分は間違っていた」と気づいたとき、その悔しさをエネルギーとして発信を続けることができます。彼らが味方になれば、そのエネルギーは社会を変える大きな推進力になるのです。
「小さな悪を叩いても、大きな悪を放置すれば意味がない」
これを忘れないでいただきたいのです。自己責任を振りかざす人そのものが悪なのではない。真に悪として断じられるべきは、自己責任論という思想そのものなのです。
改心者に優しい社会は、弱者に優しい社会でもある
自己責任論者が改心したときに、それを非難して責め立てる社会であれば、誰も自分の考えを改めることができなくなります。「一度言ったことを後から変えたら叩かれる」という空気が蔓延すれば、人々は自らの過ちを認めることを恐れ、結果として社会全体が硬直化してしまいます。
逆に、考えを改めた人を温かく迎え入れる社会は、今現在、弱者の立場にいる人々にとっても住みやすい社会です。なぜなら、そこには「誰もが学び、成長し、支え合うことができる」という前提があるからです。
おわりに - 自己責任論を撲滅するために
かつて自己責任論を唱えていた人が、さまざまな実体験を経て考えを改めることは、社会にとって大きな財産です。彼らの言葉には説得力があり、同じような価値観を持つ人々に影響を与える力があります。
彼らを責めるのではなく、優しく受け入れ、発信を促すことで、より多くの人々の意識を変えることができます。改心した人に優しい社会は、現在の弱者にとっても優しい社会なのです。
最後までお読みいただきありがとうございました。