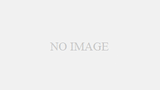2024年9月、自民党総裁選のさなか、同党の小泉進次郎氏はいわゆる「解雇規制」に触れ「解雇規制を見直す。人員整理が認められにくい状況を変える」と述べました。
この発言が「社員のクビを切りやすくすべき」と解された結果、党内における小泉氏の支持率を下げ、結果として敗北につながったと言われています。
今回の記事では、日本における「解雇規制」の正体について、私の意見を述べたいと思います。
1. 「解雇規制」というものは存在しない
誤解している人も少なくないと思うのですが、日本には一元的な「解雇規制」というものは存在しません。諸外国と同じく、経営状況の変化(悪化)などの理由から従業員を解雇することは日本でも可能なのです。言い換えれば、日本には解雇そのものを一律に禁止する法律はないということです。
しかし日本の労働法には、解雇そのものを一律に禁止する法律はないものの、労働契約法第16条をはじめとする規定により、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」には無効とされます。この「解雇の有効性」の判断が、実務上非常に厳格であるため、「解雇しにくい」という印象を与えている面があります。
2. 解雇後の訴訟リスクが企業側に負担を与える
実際には雇用者と被雇用者の間で合意が得られた解雇、いわゆる「円満解雇」であったとしても、その後に解雇された従業員が「あれは不当解雇だった」などと主張して訴訟を起こした場合は、企業側はどう対応したらいいのか?
これは多くの企業が直面している問題です。従業員が解雇後に不当解雇を訴える場合、上述した労働契約法によって、企業はその解雇が「合理的かつ適切であった」ことを立証する責任を負います。
たとえ企業が勝訴したとしても、以下のコストが伴います:
- 裁判にかかる時間的・経済的負担
- 社会的信用の毀損・企業イメージの低下
特に中小・零細企業においてはこうした時間的・経済的なコストはとうてい許容できないケースが多いでしょう。こうした背景から、多くの企業が「訴えられるくらいなら解雇を回避する」方針を採る傾向があります。
3. 「訴えられたら負け」の状況
法律上、企業が必ず敗訴するわけではありませんが、実務上は訴訟リスクを恐れる企業が多いのは事実です。これは、以下の理由によるものです。
- 日本の司法(裁判所)は、従業員保護を優先する傾向がある
- 解雇の有効性を認めるための要件が非常に厳しい
- 裁判そのものが長期化しやすく、企業経営に悪影響を与える
まとめ:「解雇規制」は特定の法改正では容易に解決できない問題である
日本には「解雇規制」という一元的な規制は存在しません。解雇規制の正体とは、様々な要因によって生じている現象といえます。
ですので単純に法改正を行って「解雇をしやすくする」だけでは、企業と従業員の関係性や、日本社会特有の「終身雇用」文化、社会的合意の問題を解決することは困難です。さらに、労働者の権利保護とのバランスを考慮しなければ、雇用の安定性を損なうリスクもあります。
一元的な規制緩和や単純な法改正だけでは根本的な解決にはつながりません。この問題を解決するには、労使双方が納得できる新たなルール作りや、訴訟に至る前に解決できる仕組みの整備が必要です。
個人的には「解雇規制の緩和」を主張する人について「規制がゆるくなるのか!それはいいことだ!」「クビを切りやすくするなんて許せない!」などと短絡的にとらえるのではなく、具体的にその人が、
- 「何と戦おうとしているのか?」
- 「具体的にどのような世界を目指しているのか?」
といったことを様々な観点から考える必要がある、と思っています。