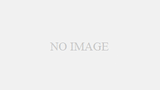日本における発達障害者向けの就労支援や就業訓練施設は、基本的に
「発達障害者を定型発達者の社会に適応させる」
ことを主眼としてプログラムが設計されています。
このアプローチは、社会全体が発達障害者の特性を理解し、相互理解を進める共生社会の実現を目指すものではなく、発達障害者に一方的な「矯正」を求めるものとなっている点で問題があります。
今回の記事では、現状の発達障害者支援が持つ問題点について私見を述べたいと思います。
発達障害者支援の問題点
冒頭で述べたように、現状の発達障害者支援は、問題のある側は発達障害者のほうであり、いっぽうの定型発達者のほうは問題がないとしたうえで、一方的に発達障害者に「本来持っている特性」を殺すことで、定型発達者が望むように生き方を変更することを強いるものとなっている側面があります。
たしかに、これらの施策によって救われる発達障害者は存在するでしょう。特に、発達障害の診断には至らないものの発達障害の特性を持つ「発達グレーゾーン」の人々にとって、社会参加の貴重な機会となる場合もあるでしょう。
しかし、現状の支援の構造を人種問題に例えるなら、
- 「黒人の皆さん、白人のように扱われたければ肌をホワイトニングし、外見を白人に近づけましょう」
- 「アジア人の皆さん、あなた達の顔は平たく鼻も低く、どうみても白人らしくない。白人社会に適応したいならば美容整形やメイクなどの努力をして白人に近づこう!」
といったような、偏見と多数派(マジョリティ)の優越感に満ちた提案と本質的に変わらない構造を持っているといえます。
つまり、多数派の論理に少数派(マイノリティ)が合わせることを強要する形は、根本的な不平等を内包しているといえるのです。
支援の限界と現実的側面
一方で、現行の支援が多数派である「定型発達者」の社会への適応を求めるかたちを取るのは、短期的な現実への対応という実際的な理由があることも我々は理解しなければいけません。
現在の社会や労働市場が即座に大きな変化を成し遂げることは難しく、現状では発達障害者自身がある程度、既存の枠組みに適応するスキルを得ることが必要とされているのも事実です。
ただし、このような現状維持的な支援は、「共生社会の実現」という長期的な目標を後回しにしている側面があります。発達障害者の多様な特性を尊重しつつ、社会全体が変わる努力を怠ることは、真の意味での平等や多様性の尊重にはつながりません。
適応訓練の意義
「発達障害者が定型発達者の社会に適応する訓練を受けることは短期的には効果的であり、現状の枠組みも大きな意義があるではないか」という指摘もあるでしょう。繰り返しになりますが、現状の発達障害者支援は、当事者の短期的な社会参加の促進には有効な側面があることは否定しません。
ですが、それが唯一の解決策ではなく、あくまで過渡的な措置であるべきだと私は主張します。本質的な目標は、発達障害者が自分らしく生きられる社会の実現であるべきです。
ベーシックインカムの可能性
現在の日本における発達障害者が置かれている状況がもつ構造的問題を解決するためには、発達障害者を含むすべての人が、無条件で生存を保証される制度が必要だと私は考えます。その一例がベーシックインカムの導入です。
ベーシックインカムは、全ての人に一定額のお金を無条件で支給する制度であり、生きるために必要な経済的基盤を全ての人に保証します。これにより、発達障害者も「定型発達者の社会に適応しなければ生きていけない」というプレッシャーから解放され、自分の特性や能力を最大限に活かせる活動に専念できる可能性があります。
たとえば、発達障害者が苦手な対人コミュニケーションを強いられる労働環境から離れ、自宅での創作活動や専門性を活かした仕事に集中することができるようになります。また、社会全体の労働への依存が減少することで、多様な生き方や価値観が許容される環境が生まれ、発達障害者と定型発達者が相互に補完し合う「共生社会」の実現が現実味を帯びてくるでしょう。
読者の中には、こうした感想をお持ちの方もおられるかもしれません。
- 「ベーシックインカムが導入されても、発達障害者にとって労働は社会参加の重要な手段ではないか」
- 「すべての発達障害者が創造的活動を望むわけではない。中には単純労働を望む者もいるはずだ」
もっともです。確かに、労働が社会参加の一環であることは否定できません。私はこのブログにて労働をさんざん否定していますが、本来、人間にとって労働は尊いものであったというのが私の考えです。詳しくは以下の記事をご一読ください。
ベーシックインカムは決して労働を否定するものではなく、強制的な労働を必要としない状況を作るものであり、むしろ発達障害者が自発的かつ適性に合った形で社会と関わる自由を提供する手段と私は考えます。
つまり、
- 「働きたい人は働く」
- 「働きたくない人は働かなくていい」
という選択の自由をすべての人々にもたらすもの、それがベーシックインカムという考え方なのです。
おわりに
現行の就労支援プログラムには確かに一定の価値がありますが、それが発達障害者に「適応」を一方的に要求するかたちに留まっているかぎり、真の共生社会の実現には繋がりません。
代わりに、社会そのものを変革し、すべての人に無条件で生存を保証するベーシックインカムを導入することが、発達障害者を含む全ての人の尊厳を守り、多様性を尊重する社会の実現に資するでしょう。
最後までお読み頂きありがとうございました。