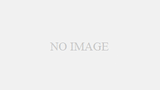1989年に事件が発覚し、世間を震撼させた「女子高生コンクリート詰め殺人事件」。
その主犯格に当たる人物が、2022年に死亡していたことが報じられました。

この事件の詳細について詳しくこの記事で解説することは控えますが、今回の記事では、この事件の加害者たちをかくも残虐な犯行に至らしめた集団心理と、おなじく集団心理である「生活保護バッシング」の類似性について私見を述べたいと思います。
「女子高生コンクリート詰め殺人事件」と生活保護バッシング
「女子高生コンクリート詰め殺人事件」と「生活保護バッシング」を関連付ける視点として、いくつかの共通する構造や心理的要素を挙げることができます。それは、集団心理の危険性や弱者への攻撃性というテーマに関連しています。
1. 弱者への攻撃と社会的構造
この事件において、被害者は物理的・心理的に徹底的に弱い立場に追い込まれた結果、加害者たちは反撃を考慮することなく残虐行為をエスカレートさせていきました。これは、絶対に反撃してこない(できない)弱者を前に、絶対的な強者の側に置かれた人々がその残酷性をエスカレートさせていったと私は読み解きます。
生活保護バッシングにおいても、経済的弱者や社会的に弱い立場の人々が「怠惰」「不正受給」といったステレオタイプを押し付けられ、社会的に攻撃される状況が見られます。この現象の特質すべき点は、こうした悪しきステレオタイプを押し付けられることにより、受給者は自分で自分を「悪しき存在」として縛ってしまうということが起きることです。
その結果として、受給者は不当な中傷や攻撃に対して声を上げることができなくなります。それも当然のことです。受給者は「悪いのは自分だ」と思い込まされているのだから。こうして「殴り放題」のサンドバッグができ上がるというわけです。
生活保護バッシングの場合も、多くの人々が反撃されるリスクのない対象である「殴り放題のサンドバッグ」に対して呵責なき攻撃を加えている点で類似性が見られます。
現代の日本では生活保護受給者を叩くことがむしろ奨励されるような風潮すらあります。生活保護受給者に弾圧を加えることがむしろ、
- 「たるんだ者たちを叩き直す世直しである。本人のためにもなる」
- 「受給者を叩いて税金のムダ遣いをなくさせるのは社会貢献だ」
などといった、誹謗中傷や弾圧が、あたかもそれが善行であるかのように解釈され得る危険極まりない風潮すらあります。
わたしは子供時代にいじめを受けていた経験があるからわかるのですが、加害者はしばしば自身の行為がまるで善行であるかのようなスタンスを取るものです。それはたとえば、
- 「コイツがいなくなればクラスがまとまる」
- 「だからコイツをいじめることには正義がある」
といったものです。この事件においても、被害者を監禁した状態が長引くにつれ加害者の視野も狭窄し、「コイツを逃がしてはならない」という倒錯した正当化の意識が働くようになったのではないかと私は考えます。
2. 匿名性と集団心理の危険性
事件では加害者たちが集団化することで、個人としての良心や罪悪感を抑え込み、残虐行為がエスカレートしました。集団の中では責任が分散し、個人の行動が正当化されやすくなります。
一方で生活保護バッシングは、多くの場合、インターネット上やメディアによる匿名的な空間で行われます。匿名性が攻撃のハードルを下げ、「みんなが言っているから」といった集団心理が攻撃を助長します。
3. 「弱者=悪」とする構図の危険性
事件の加害者たちは、被害者を人間として扱わず、物のように支配しました。この「相手の人格を否定する」姿勢が、極端な暴力を可能にしたという意見があります。
生活保護バッシングにおいても、受給者を「働かない」「税金の無駄遣い」として否定的なステレオタイプとして、ときに人間性を排除した「モノ」「カタマリ」として描くことで、彼らの尊厳や人間性を無視し、社会的な迫害が正当化されてきた傾向があると私は考えます。
4. 恐怖と無関心の連鎖
事件では、加害者の家族など、加害者以外の周囲の人々が異常に気づいていながらも、恐怖や無関心から行動を起こさなかったとされています。
生活保護バッシングにおいても、多くの人が「自分には関係ない」として声を上げない一方、攻撃する側の言論が勢いを増すことで、被害者が孤立を深める状況が作られます。
5. 社会的分断と支配の構造
こうした事件やバッシングは、社会の中に「分断」を生み出します。「弱者を攻撃することで自分の優越感を得る」という心理は、支配層や権力側が利用しやすい構造です。
例えば、生活保護受給者を攻撃させることで、社会問題の根本原因(格差や制度の欠陥)への目を逸らさせる作用も考えられます。
まとめ
このように、「女子高生コンクリート詰め殺人事件」と「生活保護バッシング」は、いずれも弱者への攻撃や集団心理の危険性を浮き彫りにしています。どちらの事例も、社会全体の倫理感や人権意識の欠如が、個人に暴力や差別を正当化させエスカレートさせる土壌を作り出していると考えられます。これらを批判的に検討することで、私たちは「弱者を攻撃しない社会」の構築に向けた議論を進める必要があります。
最後までお読み頂きありがとうございました。