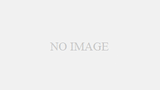日本でベーシックインカム(BI)の導入に反対しそうな人々をリストにしてみました。順序は説得が困難であろうと予想される順です。今回の記事では、BIに反対しそうな人々をどのような筋道で説得すればいいのかについても私見を述べています。
日本の世襲・寡頭制の有力者
「民を自由にさせたらろくなことにならない。金の力で自由を奪い、抑えつけておかねば秩序は保てない」
支配構造そのものが崩れるリスクがあるため、自己の権力を脅かすBIを受け入れることは難しいでしょう。根深い支配意識と民衆への不信感が背景にあるため、説得は極めて難しいと考えました。
説得の筋道
世襲・寡頭制の有力者に対しては、彼らの支配構造や利益を守る手段としてBIを提案し、社会全体の安定や経済競争力を強化する手段として位置づけることが効果的と考えます。ビジネスの利益や国の競争力向上、社会秩序の維持といった観点を強調することで、彼らの理解と協力を得やすくなるのではないか。
社会の安定と秩序の維持を強調
社会的緊張の緩和
格差拡大や貧困層の増加は社会不安を引き起こし、結果的に支配層にも不利益をもたらす可能性があることを強調します。BIが貧困層に経済的・精神的な安定をもたらすこと、ひいては暴動や社会的混乱のリスクを減少させる手段として提案できます。
秩序の維持
BIを導入することで、貧困層の不満を減らし、治安や社会秩序を維持するための手段と説明することができます。それはBIが、社会的不安定が経済活動に与える悪影響を避けるための「投資」として機能すると位置づけることです。
既得権益を守る方法としてBIを位置づける
制度の進化としてのBI
過去の社会構造や富の分配方法がもはや時代遅れであることを説明し、BIを導入することで現代の経済に適応した形で利益を維持できることを説得します。つまり、旧来の経済モデルを守りつつ、より効果的に資産を保全するための方法としてBIを提案します。
資本主義の安定化
ビジネスを基盤とした支配層が権力を持ち続けるためには、労働市場や消費市場が健全であることが前提となります。BIは、消費者市場を安定させ、ビジネスにも利益をもたらすことを示すことを説明します。
自国経済の競争力強化の手段としてのBI
グローバル競争力の強化
日本は競争力の低下が懸念されています。BIを導入することで、国民全体の生活水準や消費力が向上し、国内市場の需要が拡大し、企業活動も活性化するという点を強調します。これにより、結果として日本の競争力が強化され、支配層にも利益がもたらされると説得することができます。
社会的責任としての提案
社会的貢献の一環としてのBI
社会全体のために支配層がリーダーシップを取るという形でBIを導入することで、「国民全体の幸福を実現し、安定を確保する」という高い社会的責任を果たすことができると説明します。これにより、単なる「支配」の延長ではなく、「良い支配」としての認識を得ることが可能になると説明します。
段階的な導入と柔軟な調整
段階的導入の提案
すぐに全ての層に一律のBIを提供するのではなく、段階的に導入し、まずは低所得層や失業者層から始めるという提案をすることで、既存の経済システムに急激な影響を与えずに移行を進められることを説明します。これにより、リスクを最小化できると説得できます。
柔軟な調整
BIの導入が社会や経済に与える影響をモニタリングし、その結果をもとに調整を加えることができるシステムを提案します。これにより、経済の安定性を確保しながら、BIの実施が可能であることを示します。
富裕層
「私たちの税金が他の人のために使われるのは許せない」
富裕層は支配者層と重複する場合も少なくありませんが、ここでは分けています。一般的に富裕層は自己利益を最大化するために蓄財しようとし、社会的責任を避ける傾向が強いといえます。そのため、一部の良心的な富裕層を除けば、BIに対する拒否感は強固であると考えるべきでしょう。自己の利益を守れないと判断した場合、国外脱出(最近ではシンガポールあたりか)も選択肢として取りうるため、説得は非常に困難と考えました。
マルクス主義者(共産主義者)
「労働は人間の本質だ」
マルクス主義者は、基本的にBIの導入に対して否定的な立場をとることが多いです。その理由は、「労働こそが社会を支え、人間を自己実現へと導く」 という基本的な考え方にあります。彼らにとって、労働は単なる生活の手段ではなく、人間が社会と関わり、階級闘争を通じて資本主義を克服するための重要な要素なのです。
BIは労働を必要としない所得を提供するため、「労働者の階級意識を希薄にし、団結を阻害する恐れがある」と解釈されるでしょう。さらに、BIは資本家による生産手段の私有を温存したまま所得を分配する仕組みであるため、資本主義の根本的な変革(打倒)にはつながりません。そのため、彼らは「労働者の真の解放は生産手段の共有化(国有化)によってのみ達成される」と主張し、BIを資本主義の延命策と見なして批判するわけです。
説得の筋道(極めて困難)
マルクス主義者の思想は、単なる政策論ではなく、資本主義そのものを否定する歴史的なイデオロギーに根ざしています。そのため、短期間でBI支持へ転向させるのは難しく、むしろ対立を生む可能性が高いでしょう。BIの推進を進める上では、彼らを説得するよりも、より広範な一般層や、労働環境の改善を求める人々に訴えかける方が現実的であると言わざるを得ません。
資本家(企業経営者)
「働き手がいなくなったら困るし、BIを導入されたら賃金交渉が激化するのではないか」
資本家にとっては、労働力を安く抑え、資本を増やすことが前提となるため、BIによる労働市場の変化は基本的に歓迎されないでしょう。特に低賃金労働が減ることで利益率が低下することを懸念するはずです。業種によってはBIに適合するためには既存のビジネスモデルを根本から見直す必要もあるでしょうから、そこまでしてまでBI導入を支持するとは考えにくい。
説得の筋道
資本家に対しては、BIが自社の利益を増加させる可能性を訴えることが重要と考えます。市場の拡大や労働市場の安定、社会的責任を果たす手段として、BIを導入することが企業の成長にもつながる点を強調し、彼らの経済的利益と社会的評価の両方を意識した説得をすることです。
消費市場の拡大
BIは市場の需要を増加させる
BIによって、消費者の購買力が向上し、特に低所得層の消費が増加します。これにより、商品やサービスの需要が高まり、資本家のビジネスにも利益をもたらす可能性があることを説明します。
購買力の底上げ
現在、低所得層は消費を控えがちですが、BIが提供されることで、安定的な消費市場が創出されるため、企業は安定した需要を見込むことができるようになります。これにより、企業の成長を支える安定的な消費者層を得られることを説明します。
労働市場の安定と効率化
労働市場の柔軟性を高める
BIにより、従業員がより自由に職業選択をできるようになり、企業側もより効率的で質の高い人材を採用しやすくなるという点を説明します。これは企業がより優れた人材を求めやすくなる一方で、賃金や労働環境の改善にもつながります。
BIによって生活が保証された社会では、「一度手にした社員のポジション」にしがみつく人は減ります。
低賃金労働の減少
低賃金労働に依存することなく、従業員が自分の価値に見合った仕事を選びやすくなります。これにより、企業は、よりモチベーションや能力の高い働き手を確保でき、長期的には生産性の向上が期待できると説明します。
働きたくない人を無理やり働かせるような社会においては、ときに人命にかかわる不幸な事態が発生するリスクがあります(警備、介護、建設など)。BIがあることにより本当にその仕事に従事したい人が仕事を求めるようになります。
労働者の健康と幸福の促進
従業員の福利厚生向上
BIを導入することで、働く人々は過度な労働から解放され、健康的でバランスの取れた生活を送ることができるようになります。健康で満足度の高い従業員が多ければ、企業の生産性や創造性も向上します。
企業の社会的責任(CSR)
BIは企業が社会的責任を果たす手段として位置づけることができます。社会全体が安定し、消費者の生活の質が向上すれば、企業のブランド価値や社会的評価も向上します。
税制や政府の支援を強化
税負担の軽減
一部の資本家は、BIの導入を政府の新たな支出として懸念しますが、BIは経済全体を活性化させ、最終的には税収の増加につながる可能性があります。企業活動の活性化により、企業の税負担も相対的に軽減する可能性がある点を説明します。
政府との協力
企業は政府と協力して、BIによる経済成長をサポートし、最終的には企業が利益を得る環境を整えるための政策を提案することができます。
イノベーションと創造性の促進
自由な時間が創造的なイノベーションを生む
BIを通じて得られる自由な時間が、働く人々の創造性やイノベーションを促進します。これにより、新しい商品やサービスが生まれ、企業の競争力を強化することが期待できます。
リスクを取る文化の育成
BIが安定した生活を提供することで、リスクを取ることへの心理的な障壁が下がり、新しいビジネスや技術革新のチャンスが増えることを説明します。
社会的な不安の解消と秩序の維持
社会的な安定が経済を支える
BIによって貧困層が安定し、社会的不安が減少することは、ビジネスにとってもリスク管理の一環となります。社会的な不安が解消されることで、企業はより安定した経済環境で活動できるようになります。
伝統的な家族観・性別役割を重視する層
「男は働き、女は家庭を守るのもの。BIなんか導入されたら家族の絆が壊れる」
BIには「個人の自立」を促す側面があるため、保守的な価値観を持ち、「現代日本は個人主義が過ぎる」と考えている人々は、「BIなんか始めたら家族制度が崩壊する」と警戒することが予想されます。専業主婦が経済的に自立できることや、夫婦間の経済的不均衡が是正されることを脅威と感じる可能性があるということです。
説得の筋道
「伝統的な家族観・性別役割を重視する層」を説得するためには、伝統的な価値観を尊重しつつ、社会の変化に対応する重要性を説明し、家族の安定や男女の役割に関する柔軟性が社会にとっても有益である点を強調することが有効と考えます。以下のような建設的な提言が考えられます。
家族の安定と幸福を強調
家庭の経済的安定を支える手段としてのBI
BIは、家計に安定した収入をもたらし、家族全体の経済的な安心を確保するための手段として位置づけられます。これにより、両親が共働きしなければならないプレッシャーが軽減され、家庭内での役割分担がより柔軟になり、家族の絆を強化することができると説明します。
家族の価値観の維持
BIによって、家庭内での役割分担や子育てが支援されるため、伝統的な家族観に沿った形で家族生活が守られやすくなります。家庭内での父母の役割を重視しつつ、共働きの負担を軽減できることを示します。
伝統的な価値観と個人の自由のバランス
男女平等と家庭の価値観の両立
伝統的な家族観を重んじる層には、男女の役割分担を大切にしていることが多いため、BIを通じて「家庭内での父親と母親の役割」を保ちながらも、同時に女性の社会参加を無理なく支援できるという点を説明します。女性が家庭に専念できる環境を整えつつも、社会の進展に合わせた柔軟な働き方を支援する方法としてBIを位置づけることができます。
家庭内での選択肢を広げる
BIは、従来の「一方が働き、もう一方が家庭を支える」という伝統的な家族観を尊重しつつも、家族全体にとって有益な選択肢を増やす手段として活用できることを説明します。BIにより、家庭にいる親が経済的に困ることなく、子どもの教育や育成に集中できる環境を作ることが可能です。
地域社会と家族の支援
地域社会の活性化を促進
BIについて、地域社会全体に広がる経済的余裕を生み出し、家庭や親子の支援に充てることができる資金を確保する手段として説明します。これにより、伝統的なコミュニティの強化や、家族のサポートネットワークの形成を促進することができます。資本主義市場に飲み込まれ、運営が困難となり消えかかっている伝統的なコミュニティの保全にBIが有用であると説明します。
地域での相互扶助の推進
伝統的な家族観の中で大切にされる相互扶助の精神に基づいて、BIが社会全体で助け合う仕組みを強化するものであることを示します。BIとは相互扶助そのものであるといえます。地域社会が繁栄し、家族が安心して生活できる土台を築くための手段としてBIを説明することができます。
家族の多様性を認める視点
多様な家族形態への理解を促進
伝統的な家族観を重んじる層には、現代の多様な家族形態に対する抵抗感があるかもしれませんが、BIは家族の選択肢を広げるものであることを説明します。例えば、共働きの家庭や、シングルペアレントの家庭など、さまざまな家族のあり方が尊重されるべきであるという視点から、BIはその自由を保障する手段として位置づけることができます。
変化に柔軟に対応できる社会をつくる
BIは、社会全体が時代に応じて変化する中で、伝統的な価値観を尊重しつつも、変化に柔軟に適応していける社会をつくる手段であることを示します。
仕事と家族のバランスの改善
働き方改革を支援する
伝統的な家族観を持つ層に対して、BIが働く親にとっての負担軽減になり、仕事と家族生活のバランスを取りやすくする点を強調します。特に、母親が家庭内での役割を全うしつつも、外で働かなくても生活できる基盤を提供できる点を説明することが重要です。
家庭の外で賃労働に従事したい人はそうすればいいし、家庭に専念したい人はそうすればいい。人々がその選択肢を得られることが重要なのです。
安心感と精神的な安定
家族全体の安心感を提供
伝統的な家族観を大切にする人々にとって、家族の経済的な安定は非常に重要です。BIは、家族全体の生活を支える安定的な基盤を提供し、不安定な労働市場や経済的困難から家族を守る手段として強力に機能します。これにより、家族に対する責任感が強い層にとって、BIが家族を守るための重要な支援策となり得ることを説明します。
中間層(特に「自力で成功した」と思っている人)
「俺は努力してここまで来たのに、なんで働かない人間に金を配るんだ?」
自分の成功要因から運の要素を都合よく排除し「すべて自分の努力の結果」と考えているため、BIによる平等化を不公平と感じることが予想されます。特に、学歴や資格、努力を積み上げた自負がある人ほどBIを嫌う傾向があるといえます。この思考は後述する「ネグレクト・スパルタ育ちのトラウマを抱えた人」とも重なる部分が多い。
しかし、BIが中間層にも恩恵をもたらすことを示せば、説得できる可能性はあると考えます。
低賃金労働層(特にブラック企業の従業員)
「BIなんか導入されても、俺たちは結局働かなきゃならない。どうせ貧乏のままだろ」
一見BIの恩恵を受けそうな層ですが、「どうせ社会は変わらない」と諦観している人々はBIに対しても懐疑的であることが少なくない。ブラック企業に縛られていると、自分が搾取されていることに気づきにくく、現状を受け入れてしまうことがあります。
極めて搾取的で不公平な環境におかれているにも関わらず「仕事があるだけありがたい。社長は本当に偉い人だ。感謝せねば」というのがその好例です。こうした背景から、「BIがあれば自由になれる」と納得させるのは意外と難しいと考えます。
政治的な保守層(国家主義・愛国主義的な人々)
「国家が国民に金をバラまくなんて、社会主義への第一歩だ!」
BIが「国家による富の再分配」と見なされ、資本主義の原則に反すると考える人々です。特に「国家は小さくあるべき」とするリバタリアンや、国民の自立を美徳とする保守派は反発しやすい。「国家による監視」を危惧して反対する人々も少なくないでしょう。しかし、BIを「自由市場を活性化する政策」と説明すれば、説得は可能ではないかと考えます。
ネグレクト・スパルタ育ちのトラウマを抱えた人
「自分が苦しんできたのだから、他人も苦しむべき」
「自分が苦しんできたのだから、他人も苦しむべき」という心理が強く、利他的な行動を否定する傾向が強い。他人の幸福を素直に喜べないため、BIの恩恵を素直に受け入れられない。ただし、心理療法などで価値観が変わる可能性はあるため、根気強い説得により転向を促すことは不可能ではないと考えます。
「私は仕事をしていないと堕落してしまうだろう。みんなもきっとそうだろう」派
「仕事をしなくなったら、みんなダメ人間になっちゃうだろ」
自他境界が明確でない個人が多く、自分の価値観を他者に押し付ける傾向が強い人も少なくない。BIを導入すると社会全体が怠惰になると信じ込んでいる。しかし、成功しているBIの事例や、個々のライフスタイルに合わせた働き方を提示することで、考えを変える可能性があると考えます。自他境界の曖昧さは、反面、心理的防壁の希薄さでもあります。
既存の福祉制度に関わる人々(公務員・NPO・福祉団体)
「BIが導入されたら、私たちの仕事はどうなるの?」
現行の福祉制度がBIに統合されると、社会福祉関係の公務員やNPOの活動が縮小する可能性があります。そのため、「BIを導入すると自分の仕事がなくなるのでは?」と恐れる人々が出てくることが予想されます。ただし、BIと既存の福祉が共存できることを説明すれば、一部は理解を示す可能性もあります。
「そんなうまい話があるわけない」懐疑派
シンプルに懐疑的なだけなので、既にBIに対して興味を持っている可能性も高く、データや事例を示せば納得する可能性は高い。一度理解すれば、逆にBIの推進派に回ることもあり得る。最も説得しやすい層と考えます。